 |

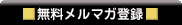 |
 |
『 手帳の達人 』
多くの人が手帳の方法に固執してしまい結局長く手帳を書き続けられない。そんな方にこそ読んでもらいたい
|
|
 |

 
|

 |
哲学の欠点 |
|
 |
学問の王者=哲学。 探求することの最上レベル=哲学。
そんな哲学だからこそ欠点も伴う。
● 哲学者など滅多に現れない
哲学は学問の王様である。この道は本当に険しい。
その到達点は遥かに高い。
哲学の欠点があるなら、哲学自身の高みにある。
この高みゆえに、哲学者など滅多に現れないことである。
1世紀に1人出れば良いほうだ。
同時代には大抵1人である。多くて2人である。 それ以上は生まれない。
だから哲学を専攻する者は以下のいずれかに属す以外にない。
哲学学者・哲学者研究家・哲学愛好家である。
大学教授、名誉教授、世界的哲学者と呼ばれる人のほぼすべてが
真の哲学者のレベルにまったく届いていないというのが残念ながら実情である。
動画 テキスト
● 哲学の道は険しさ
哲学の道は非常に厳しい。
数学はア・プリオリな直感を基礎におく。
物理学はア・ポステリオリの自然力(=重力、電磁力、・・・)の探求である。
しかし数学者も物理学者もそのことをまったく意識しない。
哲学はその両方の基礎となる認識を強く意識する。
その認識の区別を知り、その認識で人はどこまで理解できるうるかを探求する。
その認識手法をもってこの世界の姿に論理的な光を照らす。
哲学の対象はこの世界すべてである。
この世界の姿そのものと対峙する。 学ぶべきことは驚くほど多い。
過去の偉大な頭脳によって、既に確立された地点も深遠である。
哲学の道は真理への道である。
真理以外にこの道はないと心すること。
哲学の道はそれだけ厳しい。
真の頭脳を有する者しか受け付けないのである。
動画 テキスト
● 哲学と孤独
哲学の道には孤独が付きまとう。
真の哲学者はめったに生まれない。
現在、哲学を専攻する人のほぼすべては哲学者ではなく、哲学学者、
哲学研究家というところである。
真の哲学者のレベルに到達したときに目に見える風景は山の頂上から眼下
を見下ろしたごとくすべてが見える。
彼の見る世界は、そこに到達したものだけが見れる世界である。
高みに到達した哲学者が心から真理について語れる友を得ることは難しい。
山の頂上に近づくほど、その数は常に少数の人に限られてくるものだからだ。
哲学の道においては好敵手という友を期待しても滅多に現れないものである。
社交的で知られたカントであるが話題が哲学になると不機嫌になったのだ。
社交とはいえ、あのカントに哲学の話を持ちかけるなんて、その人は余程の
レベルにあると思っているのだろうか(笑)
動画 テキスト
● 哲学と独身
その高みに至るまでに真の哲学者はすべてを探求することに費やす。
その結果、本物の哲学者は皆独身となる。
プラトン、デカルト、スピノザ、ロック、ヒューム、ゲーテ、カント、
ヴォルテール、 ショーペンハウアー 皆独身であった。
すべてを捧げても掴みがたい物=真理
超一流の頭脳が探求にすべてを費やしても近づきがたい真理=哲学。
どんな人間であれ異性といることで安心感、安堵感が生まれるものだ。
生きる上で男にとっては女が、女にとっては男が精神的な安心感を与える。
異性と生活を共にしない生活は、自然的状態からは大きく離れる。
多くの愛情を有していていた深遠な者たち。
それでも彼らは独身を貫き、おそれず孤独の中を進んでいった。
動画 テキスト
● もう一度 哲学の孤独
孤独はそれだけではない。
真理にたどりつき、仮に哲学体系を打ち立てる栄誉にあってもその哲学者が
生きている間にその誉れに預かれることは少ない。
彼が生み出したものを理解できる人は極々、少数である為だ。
そのレベルにある程度近づけるの者でさえ常に少数である。
いつの時代も真の哲学は常に少数の人々に支持されてきた。
この事情は科学界(物理、数学)にもある。
遥かに進んだ研究成果を発表しても周りが理解できず、その真価が理解され
評価されるのがその科学者が死後ということが往々にある。
科学でさえこうである。
探求の王道=哲学においてはこのスパンが遥かに長くなるものだ。
哲学者の死後200年を経て、その業績が世に知られるというのも珍しくない。
『 真理の登場は常に少数の人々によって見守られる 』
動画 テキスト
● 哲学は哲学を飲み込む
哲学はその性質上、それ以外の哲学をすべての飲み込む(包括する)。
あの哲学が成り立ち、この哲学が成り立つということはない。
哲学が真に進んだとき、その哲学はその過去の哲学すべてを飲み込む。
だから真の哲学の道には○○学派、○○主義などという言葉などないのだ。
あるのは真理のみ。
カントの哲学が世にでるとそれ以前の哲学はすべてここに流れ込んだ。
ショーペンハウアーの哲学がでて、それ以前の哲学は全てここに包括された。
動画 テキスト
● 哲学は成果が見えにくい
哲学の道は険しく。その功績は科学者よりもはるかに大きい。
だがその結果が直接、多くの人々の目に見えることは少ない。
科学においてはその成果は最終的に実用的なもので表現される。
車・飛行機・ロケット・電気製品・通信インフラ等々
日々の生活に大いに役立ち、多くの人の目につきやすい。
科学者の思想を根底で支えるのが哲学者の役目である。
その成果を目に見えるものへ直結させるのが科学者であり、技術者である。
| → 目に見える成果
哲学者 ⇒ 科学者 ⇒ 技術者
だがその科学者達でさえ彼らが日頃、探求する上で判断の基準としているもの
が哲学の成果であることに気づくものは少ない。
動画 テキスト
● 偽者が跋扈しやすい①
数学においては偽者は活躍できない。
数学分野において文科系のように権威者という存在はほとんど聞かない。
なぜなら、どれほど名が知られた老年の数学者が主張しようが、無名の若者が
証明しさえすれば、若者のほうが数学では真実であるからだ。
これは物理学者でも事情は同じである。
証明がいらない文科系では事情は反対になる。○○学派、○○論者など
考えごと、昔の学者ごとに派閥を組んで分かれる。
結局どうでも良いことがほとんどである。
数学は脳の直感=ア・プリオリを基礎におく。だから数学は世界で同一に帰す。
アメリカ数学や日本数学というものなどはない。皆、同じ数学なのだ。
物理は脳の経験的認識=ア・ポステリオリを基礎におく。
物理学も数学同様に世界で同一に帰す。
アメリカ物理や日本物理などというものはない。
物理学は実験を通して必ず保障されることが真実であるからだ。
地球上のどの国でもいつでも条件が整えば現象が発動されることを根拠に置く。
だから法則というのだ。
動画 テキスト
● 偽者が跳梁跋扈しやすい②
されど哲学はその成果が直接、世の中に出ることはまれである。
哲学は一流の探求者の判断の基礎となり支えるが、それにより生み出された
成果を受け取るのは科学者や技術者である。
カントの証明を見れば、それが真実であることがわかる人にはわかる。
だがその深遠さゆえに本当に理解されることは稀であり、またそれを目に
見える形で示すことはもっと大変なことである。
だから哲学の周りには偽者が多数集まる。
○○学派、○○派哲学などと派閥を形成し、その延長上でしか考えられない
程度の頭脳が跳梁跋扈する。
そういう連中の特徴は、真理を愛するのではなく、自分が学んだ哲学者の
思想や自分が学生時代に慣れ親しんだ考えを愛する。
本来、哲学は1つに帰する。 真理は誰にも共通であるからだ。
動画 テキスト
(*) 詳細は以下のサイトを参照。
『 稲穂黄金の深遠なる者達 』
『 稲穂黄金の浅はかなる者達 』
● 哲学はもっとも知的満足を与える①
いままで哲学の欠点を述べてきたが、最後に哲学の良さを述べよう。
それはなんといっても哲学は知的満足をもっとも得られる学問であることだ。
どんな学問であってもある程度の知的満足は得られる。
だがその学問が論理的基盤から離れるごとに知的満足の度合いは減少する。
たとえば文科系の学問である。どれほど確実な基盤を置き、論理的な展開を
試みても、そこには科学などに見られる確実性、正確性が欠ける。
歴史学や経済学などもこの範疇に入る。
経済学は人の感情の総体の動きをその基礎におく。
しかし基礎がたえず幅のある動きを休まずする為に経済活動の結果は
大まかな範囲を指し示すに過ぎない。ざっくばらんというところだ。
動画 テキスト
● 哲学はもっとも知的満足を与える②
科学はいつでもどこでも条件が同じならば、同じ結果を示す。
法則というのは科学において正確無比さを発揮する。
哲学の満足は科学をも遥かに凌駕する。
数学はア・プリオリな直感を基礎におく。
物理学はア・ポステリオリの自然力(=重力、電磁力、・・・)の探求である。
数学者も物理学者も意識せず行う探究活動の奥で行われている認識について
哲学者は熟考する。 哲学はその両方の基礎となる認識を強く意識する。
認識を区別し、その認識で人はどこまで理解できるかを探求する。
哲学の道は確かに険しく、宝物(=真理)などには滅多に出会えない。
だがその道は確かに王道である。 探求者の王道である。
哲学の道を進む若者に真理の祝福があらんことを!
動画 テキスト
|
 |
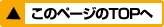 |
|  |